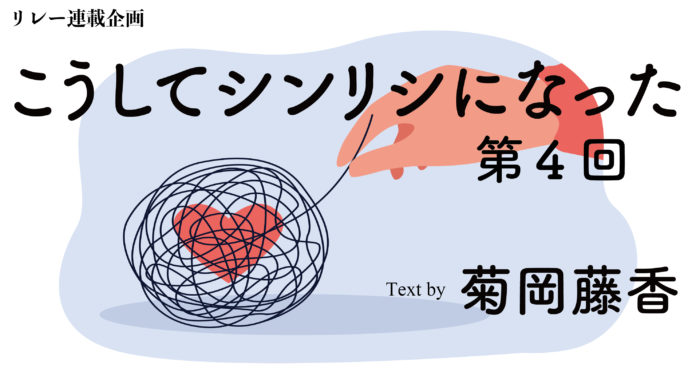菊岡藤香
シンリンラボ 第4号(2023年7月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.4 (2023, Jul.)
「シンリシになった」って,どうやったら分かるのだろう? 本誌のお題をいただいた時,私の頭の中には,真っ先にこんな思いが浮かんだ。果たして,私は「シンリシになった」のだろうか……?
シンリシのはじまり
シンリシの仕事に悩む時,いつも私はあるお母さんのことを思い出す。それは私がまだシンリシとして現場に出で2年目の頃のことである。
当時,私は地方にある総合病院で精神科所属のシンリシとして働いていた。シンリシの同僚はなく,いわゆる一人職場だった。主な業務は精神科外来での心理療法と心理検査。上司の計らいで,入職1年目は所属の精神科業務に専念させていただくことができた。
学生時代に,私は,家族療法・システムズアプローチに出会った。その理論やものの見方は私の中にスーッと入ってきて,自然と私の土台になっていった。そして,そこから導かれるように,解決志向アプローチ,エリクソニアンアプローチの先生に師事し,師の影響から,交流分析,ゲシュタルト療法,サイコシンセシスにも触れた。
治療的コミュニケーション技法によって人や場が変化していく様子はとても新鮮で,驚きの連続だった。面接がうまくなりたい。その一心で,専門書を読み漁り,面接スキル習得のためのワークショップやトレーニングに多くの時間を費やした。習得したことを実際に使い,症状や問題行動が消失したり,悩みが軽減したりその質がかわったり,クライアントにとって望ましいほうへ変化していった時には率直に嬉しく,やりがいを感じた。
もちろん,うまくいかないこともあった。トレーニングでは師から何度も叱られ,人前で数々の恥をかいた。しかし,そんな体験こそがもっとうまくなりたいという原動力になっていた。シンリシという仕事が楽しく,毎日が充実していた。
ありがたいことに精神科以外の仕事の依頼も徐々に増えてきて,入職2年目から,上司と相談をしながら,がん相談,緩和ケアチーム,小児科発達検査,職員メンタルヘルスなど,業務の幅を少しずつ広げていった。その一つに周産期センター(NICU・GCU)があり,そこで私はそのお母さんに出会った。
シンリシになにができるのか?
お母さんの赤ちゃんはNICUに入っていた。NICUは「Neonatal Intensive Care Unit」の頭文字をとったもので,新生児集中治療室を意味する。そこには,予定日より早く生まれた赤ちゃん(早産児)や小さく生まれた赤ちゃん(低出生体重児),何らかの疾患を抱えた赤ちゃんなど,集中治療や観察を必要とする赤ちゃんたちが入院している。
そのお母さんの赤ちゃんには重篤な染色体異常があり,長く生きることが難しい状態にあった。お母さんはそのことを産後間もなく知り,赤ちゃんの傍でずっと泣き続けていたという。お母さんは退院された後,毎日NICUへ足を運び,赤ちゃんに優しく声をかけたり体に触れたりスタッフと一緒に日常的なお世話をしたりして,赤ちゃんの傍で多くの時間を過ごしていた。
何の不安や訴えもなく毎日赤ちゃんの傍で1日を過ごすお母さんのことを,NICUスタッフは案じていた。
「こんな状況にあるのだから,お母さんは本当とってもつらいはずだ……」「お母さんには心のケアが必要だ……」「思いを吐き出せば,お母さんも楽になるのではないだろうか……」「シンリシならお母さんの気持ちを引き出せるのではないか……」
NICUスタッフからの強い要望を受け,私はお母さんと対面することになった。これが私のNICUでのシンリシとしての初めての仕事だった。
「スタッフの期待に応えねば……」「シンリシとして役に立たねば……」大きなプレッシャーを背負い,私はお母さんと赤ちゃんのもとへ向かった。
「でも,うまくやれるだろうか……」私は内心おののきを感じていた。しかしそれを悟られまいと,表情は過剰な笑顔になっていた。
勇気を振り絞り,お母さんに声をかけた。一言,二言……。お母さんの反応は薄かった。「何かしなければ……」私は焦った。そして,焦れば焦るほど空回りをして,かける言葉を失っていった。重苦しい空気が流れだし,「どうしたらいいのだろう……」と,私の焦りは頂点に達していた。すると,それまでじっと黙っていたお母さんが静かに,でも確かな口調でこう言った。
「シンリシだからって,あなたに何ができるというのですか」
その瞬間,私は頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けた。その後,どうやってその場を終えたのか,思い出すことができない。ただNICUを離れた後,途方もない無力感と自責の念が私を襲った。私は自分がとてもとても恥ずかしく情けなくなった。お母さんと赤ちゃんに申し訳ない思いでいっぱいで,自分を悔いた。溢れる涙が止まらなかった。
お母さんと赤ちゃんにとって,NICUは日常であり大切な生活の場だった。私はそのことに気づかなかった。いや,そうではない。スタッフの期待に応えることで頭が一杯だった私は,そのことに思いを馳せるということすらしていなかったのだ。私はお母さんと赤ちゃんの日常に土足で知識やスキルを持ち込もうとしたのだ。そこには「何かできる」という私のシンリシとしての無意識のエゴや有能感があったのだと思う。そしてそんな私の愚かさをお母さんに見透かされたのだと思う。
あの時,NICUスタッフはなぜシンリシの介入を望んだのだろう。何を思い何に悩み,そう考えるに至ったのだろうか。赤ちゃんのために,お母さんのために,できることをしてあげたい,自分たちにできることは何か…。もしかしたら,スタッフの中にも私と同じように,「何もできない」という無力感や罪悪感,葛藤があったのではないだろうか。最初に助けを求めてきてくれたスタッフに対して,私は十分に耳や心を向けることができていただろうか。面接室を離れた場で,私は自分の非力と愚かさを思い知らされた。
「何もできない」「お役に立てない」……専門家としてそれを認め受け入れることは,とても苦しく,難しい。あの時の私は,それができるだけの技量も覚悟もなく,オロオロと「何かをしよう」とした。
その日から数年。自分の中に沸き起こってくる自然なものを否定せず受け止め,ありのままをお母さんと一緒に感じたり揺れたりする。胸が痛み,本当にこれでいいのだろうかと繰り返し葛藤する。それでもじっとそこに居続けることに意味が生まれてくるのかもしれない……。そんな漠然としたシンリシの存在役割を周産期センターでの仕事を続けさせていただく中で感じるようになっていった。
シンリシのその後,そして今
家庭の事情で職場がいくつかかわり,その後,シンリシとして周産期領域に関わることはなくなった。それが数年前,期せずして,第二子出産を控えたあるお母さんの心理支援の機会を得た。
そのお母さんには持病があった。妊娠中に再発し,私が出会った時には,入院加療をしながら赤ちゃんが成長し帝王切開による出産が可能になる時期を待っている状態だった。また,お母さんは第一子出生時,体に酸素が十分に行きわたらず赤ちゃんはNICUへ入り,後にその我が子を亡くすという経験もおもちだった。
赤ちゃんが育ちおなかが大きくなるにつれ持病への負担は増加するため,お母さんの身体的苦痛は日増しに強くなる一方だった。また,第一子時にも同じような経過をたどっており,赤ちゃんが生まれてもあの時と同じことが起きるのではないか……という不安も抱えていた。
赤ちゃんの成長を守ることと自身の体調・体力の限界との狭間で,心身共にボロボロになっているお母さんを案じた病棟スタッフが,シンリシの支援を求めてきた。これまでお母さんを支えてきたスタッフの思いや葛藤をうかがいながら,そこにシンリシが関わらせていただくことで少しでも助力となれば……との思いを新たにした。
初めて病室を訪ねる時,私はあの時と同じおののきを感じていた。お母さんの苦痛を癒せる特別な方法や言葉を持っているわけではない。ただ,もしもその場に居ることが許されるなら,自分の心でありのままを感じよう……。その思いだけを胸に,大きく深呼吸をしてベッドサイドに向かった。
それから2か月半。赤ちゃんが無事に誕生し,持病の治療を終えて退院するまで,週数回の訪室が続いた。「本当にこれでよいのか…」何度もそんな思いが浮かんだ。「何かできている」という実感は一つもなかった。ただ,お母さんがシンリシの訪室を待っていてくださるようになり,それだけが私の足を病室へ向かわせていた。
お母さんの退院前日の午後。病棟スタッフから「お母さんがシンリシに会いたいと言っている」と連絡があり,夕方,病室へ向かった。これまでの労を労い,退院の喜びを分かち合っていると,お母さんがこう言った。「あの子を出産した時,NICUでシンリシさんに助けてもらったことがあったんです。シンリシさんに助けてもらうのはこれで2度目です。シンリシって素敵な仕事ですね」と。
何をもって「シンリシになった」と言えるのか……。つまらぬ屁理屈のようだが,自分が「シンリシになった」のかどうかは,よく分からない。ただ,あの日の出来事が私のシンリシとしての心構えやあり方に大きな影響を与えたことは間違いない。そしてそれは今も私の中に深く刻まれ,シンリシとしての拠り所となっている。
菊岡藤香(きくおか・ふじか)
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立豊島病院
公認心理師・臨床心理士