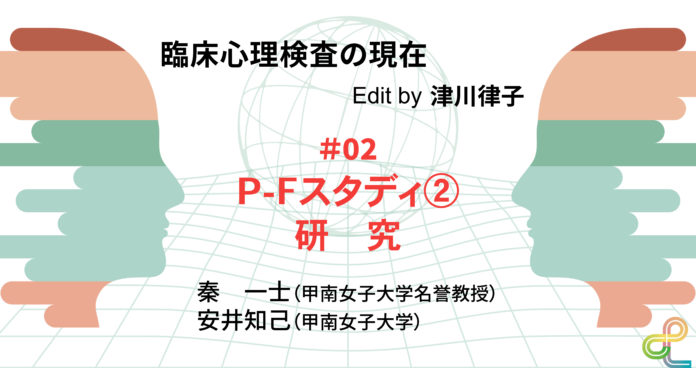秦 一士(甲南女子大学名誉教授)・安井知己(甲南女子大学)
シンリンラボ 第6号(2023年9月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.6 (2023, Sep.)
1.P-Fスタディの著書
P-Fスタディ(以下P-Fと略)の研究は,これまでに理論的,実験的,調査的な方法で広い領域にわたって実施されており,これらを概観するにはすでに出版された著書を参考にすることが望ましい。そこで,日本で出版されているP-Fの研究にかかわる主な著書を簡単に紹介しておこう。
・『ローゼンツアイク人格理論』(住田・林・一谷,1964)
P-Fに関連するローゼンツァイクの理論と実験的研究を紹介し,11種のスコアリング因子がもつ心理的意味について著者たちの考えを解説している。P-F反応から見て特徴のある事例(反応転移,GCR,E型,I型,M型の典型例と歪曲例)が取り上げられており,解釈の仕方について参考になる著書であるが,残念ながら現在は絶版になっている。
・『投影法の基礎的研究』(林・一谷,1976)
日本版を導入した林勝造および一谷彊の学位論文が一冊にまとめられた著書である。林の論文は,因子分析に基づくパーソナリティと気質との関連,アメリカ・インド・日本の比較文化的研究,場面(項目)の反応特徴について検討がなされている。一谷の論文は因子分析に基づいたパーソナリティの特徴について,多様な実験人格的研究で検討した結果をまとめたものである。
・『攻撃行動とP-Fスタディ』(Rosenzweig, 1978,秦訳,2006)
P-Fの出版以来約40年間にわたって世界各地で実施されたP-Fに関する500以上の文献を整理して,原著者が論評を加えた著書である。P-Fに関する幅広い研究方法が紹介され,文献も研究領域ごとにまとめられており,P-F研究のガイドブックともいえる書物である。
・『新訂 P-Fスタディの理論と実際』(秦,2007)
秦による学位論文を,P-Fを使用している心理の実務家向けに書き改めたものである。内容的には,反応分類の再検討,実施法とスコアリング,解釈指標のGCRや反応転移,フラストレーション反応による場面分類,テスト後の内省による質疑法の試みなど,実施から解釈に至るさまざまな問題を取り上げて検討している。
2.信頼性
一般的なテストの信頼性は項目間の同質性と,テストの繰り返しによる再検査信頼性ないし安定性の2つにわけることができる。ローゼンツァイクは,P-Fのような投映法にて内的一貫性を求めるのは不適切であり,再検査信頼性が最もふさわしいと述べている。
1)再検査信頼性
再検査信頼性については,日本の標準化に伴って成人用Ⅲ版,青年用,児童用Ⅲ版について実施されている。実施間隔などの条件によって信頼性の値は影響を受けるが,いずれの場合もGCR, カテゴリー,因子などの各指標の相関値はr=0. 4からr=0. 7の比較的高い値を示している。なお,各場面で同じ反応の再現について調べたところ,平均再現率は児童用が48%,成人用が49%であり,ほぼ半数の反応(因子)が変動しないことを示している。
2)スコアリングの信頼性
異なった評定者間におけるスコアリングの一致率についても検討されている。ローゼンツァイクによると,最終的には100名のデータについて2名の一致率は85%であり,不一致の中で5%は一致の可能性があるので,残りの10%は一致が期待できないスコアであると報告している。 日本でのスコアリング一致の信頼性は,組み合わせ方や対象数に違いはあるが,2組のペアによる平均一致率は児童用Ⅲ版が83%,青年用は83%,成人用は80%であった。
3.妥当性
P-Fの妥当性については前述のローゼンツァイクの著書に紹介されており,全体としてP-Fの妥当性を支持しているが,そのなかで以下の点については修正が必要と思われる。
1)因子分析
ローゼンツァイクは因子分析について「因子分析は,P-Fスタディのような仮説演繹的技法の妥当性の検証にはあまりふさわしい手法でない」と述べている。これは日本における林や一谷(1976)の一連の研究についての批判である。しかし,彼らの研究結果は多くの対象について,因子としてE-IとE-Mに相当する因子を抽出しており,むしろP-Fの反応分類の構成的妥当性を支持している,と肯定的に見てもよいのではないだろうか。
2)発達傾向
ローゼンツァイクは,アメリカ,インド,日本の児童用の標準化データから,共通して年齢とともに他罰反応が減少することを示して,普遍的な文化の影響が見られると結論している。しかし,日本版児童用Ⅲ版の標準化データでは,因子の出現状況について年齢的な一様の変化が見られなかったので,この結論を一般化することはできないだろう。
3)性差
「文化的な影響としての性差は,児童や成人には見られないが,青年において認められる」というのがローゼンツァイクの結論である。しかし,これまでに実施した児童用Ⅲ版,青年用,成人用Ⅲ版は,いずれも明らかに男性は女性よりも他罰反応が有意に高い結果を示しており,性差は青年に限られたことではないといえる。
4.最近の臨床的研究
1)発達障害に関する研究
発達障害を対象に,その障害特性から生じる対人コミュニケーション上の特徴やプロセスを理解するために,P-Fを用いた研究が行われている。
・児童を対象とした研究
伊藤ほか(2020)は,中学生のASD群について,GCR%が低く,U反応が多いことを報告している。満田ほか(2009)でも同様にGCR%が低いこと,U反応が多いこと,スコアリング要素では他責が多く無責が少ないことが報告されている。一方,津田ほか(2009)は,高機能広汎性発達障害と診断されている小学生23名(平均年齢8歳11か月)のGCR%について対象の70%以上が標準以上であったことを報告している。ADHD児を対象とした研究でも,健常児よりもGCR%が低く,U反応が多いことが報告されている(梅原ほか,2021)。
GCR%やスコアリング要素については一貫した結果は見出されていないが,U反応の多さを報告している研究は多く,発達障害児の特徴の1つと考えることができるだろう。
・成人を対象とした研究
成人を対象とした研究を見ると,池島ほか(2014)や白神ほか(2013)において,U反応が多いことが報告されている。青年期・成人期になって問題が表面化したASDにおいても,非ASD臨床群よりもU反応が多いという特徴が見いだされている(西藤ほか,2021)。
GCR%については緒方ほか(2019)では標準範囲よりも低いことが報告されている一方で,池島ほか(2014)では標準範囲内であった。また,池島ほか(2014)の研究では,そのほかのスコアリング因子についても個別に見ると標準範囲から外れる者も見られたが,一貫した傾向は認められなかった。井上ほか(2019)では,ASD群のGCR%はコントロール群よりも有意に低いものの,70%以上の対象者も存在していたことが報告されている。成人のASDにおいても,U反応の多さはASDの特徴を示す指標の1つとして示唆されている。
・反応や場面に関する質的分析
ASDを対象とした研究ではまた,U反応の具体的な内容について検討されている。満田ほか(2009)は,児童のU反応について4つのカテゴリーに分類し,「単純了解反応」「場面理解失敗反応」「説明不足反応」「意味不明反応」の順に多く出現していたことを報告している。成人についても,西藤ほか(2021)や白神ほか(2013)は,場面誤認や状況にそぐわないU反応の出現を認めている。また,U反応が多く認められる場面として,場面に至る文脈や背景の推測が必要となる複雑な場面や第三者が登場する場面などが指摘されている。
西藤ほか(2021)は,ASD群の回答内容に関する質的分析を行い,「過度な他責」「共感性に乏しい自己主張」「状況に不適当な発言」「違和感のある語用」の4つの特徴が認められたことを報告している。
2)臨床群を比較した研究
非行や虐待など攻撃性と関わる問題や,情動の表出・抑制が要因と考えられる疾患に関して,その心理的特徴を明らかにするためにP-Fが使用されている。
緒方(2009)では非行児のP-Fの特徴について分析し,非行群は対照群に比べ,E-Dが多く,I_が少ないことを報告している。また,緒方(2017)では非行児のP-Fの反応についてテキストマイニングによる分析を行っている。その結果,非行児ではいくつかの場面で反応の文字数そのものが少ない傾向,「嫌」「なんで」も対象児よりも少ない傾向が認められ,これらの結果について言葉で適切に自己主張できないという非行児の特徴と考察している。
そのほか,武田(六角)(2000)ではうつ傾向の子どもはE-A,E-E_が高く,I-A,M-A,I_,I-I_,M-A+I_が低い傾向があったこと,浅野ほか(1999)では小児心因性難聴の症例においてE-Aが低く,I-A・M-Aが高い事例が多かったことが報告されている。
3)処遇効果に関する研究
高岸ほか(2014)は,受刑者に対して行われる認知行動モデルに基づく改善指導プログラムの効果検証を行っており,怒りの統制および問題解決法に関する補助ツールとしてP-Fを用いている。検証の結果,プログラム後にはN-Pの上昇,E-D,GCRの減少という変化が認められ,プログラムによる問題解決法の積極的変化を反映するものと考察している。同じく司法領域で,堀尾・菊池(2007)は更生保護施設での処遇効果について縦断的な検討を行っている。この研究では,P-Fの10場面のみを使用しているが,Eの減少,I_やiの増加が認められたことを報告している。このような司法領域の研究では,対象者が社会的に望ましい反応をする可能性があり,効果の評価は慎重に行う必要があるだろう。
その他,アサーション訓練後ではP-Fの他罰反応が増加し,内観療法では逆に他罰が著しく減少するというように,処遇の期待する方向に変化する研究結果が示されている。
5.研究上の留意点
これまでの臨床的研究を検討した結果から,研究上の留意点について述べておこう。
1)臨床群の特徴
特定の臨床群についてP-Fを実施して指標注1)の特徴を見た研究がある。たとえば一谷ら(1974)は,不登校(登校拒否)を対象にしてP-Fの反応タイプと予後との関連を見た研究で,E型やI型に比べてM型に予後不良が多いことを見出している。この結果は,同じ臨床群内でもP-F反応の違いに意味があり,単に臨床群をひとくくりにしてP-Fの指標を比較することの問題点を示唆しているともいえるだろう。
注1)P-Fの反応は3つのアグレッション(反応)の型と方向というカテゴリーや因子,GCR(集団一致度),反応転移などの解釈に参照する指標をまとめて,スコアリング要素ないし指標としている。
2)スコアリング
P-Fの研究でスコアリング指標を取り上げる場合に,スコアリングの適切さを示す手続きを明示することが要請される。一般的には,複数の評定者によるスコアリングの一致度を示し,不一致の場合にどのような処理をしたかが明らかにされなければならない。一致度はおよそ80%が目途になるだろう。
3)処遇前後の比較
臨床的ないし教育的な処遇の前後にP-Fを実施して,処遇の効果を見る研究がある。多くの場合に,処遇直後にはP-F上の変化が見られるが,時間がたつと元に戻る傾向も認められている。したがって,事後の調査にはテスト実施時期の要因を考慮しなければならない。
4)事例研究
事例研究の場合に,資料として整理票だけでなく,プロトコル(生の反応)をどのようにスコアリングしたかを示すべきである。さらに,実施の方法としてテスト後の質疑を含むことも重要である。P-Fは投映法であり,一般化されたスコアリング指標だけに基づいた解釈では,事例の個別的解釈として物足りない。
文 献
- 浅野恭子・小川郁・井上泰宏ほか(1999)小児心因性難聴における心理的要因の変化.Audiology Japan, 42; 126-130.
- 秦一士(2007)新訂 P-Fスタディの理論と実際.北大路書房.
- 林勝造・一谷彊(1976)投影法の基礎的研究─Rosenzweig P-F Studyを中心として.風間書房.
- 堀尾良弘・菊池直(2007)青少年に対する更生援助の処遇効果に関する検証—P-Fスタディを用いて.愛知県立大学児童教育学科論集,41; 19-34.
- 一谷彊・津田浩一・飯田美智子・出井康子(1974)登校拒否児の性格と予後(Ⅰ)―Rosenzweig P-F Studyにみられる反応様式と予後調査との関係についての検討.京都教育大学紀要,Series A., 44; 1-20.
- 池島静佳・篠竹利和・高橋道子ほか(2014)高機能広汎性発達障害におけるP-Fスタディ(成人用)の特徴.心理臨床学研究,32; 137-143.
- 井上勝夫・緒方慶三郎・滝澤毅矢ほか(2019)成人自閉スペクトラム症診断とP-Fスタディの集団一致度の関連.北里医学,49; 79-85.
- 伊藤瑠里子・堀内史枝・河邉憲太郎ほか(2020)思春期自閉スペクトラム症における対人関係障害のスクリーニングツールの検証―P-Fスタディ児童版を用いて.最新精神医学,25; 229-233.
- 満田健人・明翫光宣・辻井正次(2014)PFスタディ反応における広汎性発達障害児と定型発達児の比較研究.小児の精神と神経,49; 221-230.
- 緒方慶三郎・井上勝夫・滝澤毅矢ほか(2019)成人ASDにおけるP-Fスタディを用いた集団一致度(GCR)とASD特性との検討.精神医学,61; 205-212.
- 緒方康介(2009)児童相談所における被虐待児のP-Fスタディ反応の分析.犯罪心理学研究,47; 37-45.
- 緒方康介(2017)P-Fスタディに対する非行児の言語反応—テキストマイニングによる解析の試み.犯罪学雑誌, 83; 118-129.
- Rosenzweig, S.(1978)Aggressive Behavior and the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Praeger.(秦一士訳(2006)攻撃行動とP-Fスタディ.北大路書房.)
- 西藤奈菜子・川端康雄・若林暁子ほか(2021)P-Fスタディを用いた診断閾下の自閉スペクトラム症を有する青年・成人のアセスメント.心身医学,61; 64-74.
- 白神智絵・筒井道子・萩原利香ほか(2013)高機能広汎性発達障害者のP-FスタディにおけるU反応の検討.日本心理学会第77回大会発表論文集,286.
- 住田勝美・林勝造・一谷彊(1964)ローゼンツアイク人格理論.三京房.
- 高岸百合子・堀越勝・勝田浩章(2014)反犯罪性思考プログラムの受講が受刑者の怒りの統制と問題解決法に与える影響—認知行動モデルによる一般改善指導の効果の検討.犯罪心理学研究,52; 31-45.
- 武田(六角)洋子(2000)児童期抑うつの特徴に関する一考察—攻撃性を手がかりに.発達心理学研究,11; 1-11.
- 津田芳見・橋本俊顕・森健治ほか(2009)高機能広汎性発達障害のある幼稚園児・小学生における認知・行動発達に関する検討.脳と発達,41; 420-425.
- 梅原碧・近喰ふじ子・都築智子ほか(2021)注意欠陥・多動症児に対するP-Fスタディからとらえた主張性に関する研究.東京家政大学研究紀要1人文社会科学,61; 79-84.
秦 一士(はた・かずひこ)
甲南女子大学名誉教授
資格:臨床心理士
主な著書:『攻撃の心理学』(共編訳,北大路書房,2004),『攻撃行動とP-Fスタディ』(単訳,北大路書房,2006),『新訂P-Fスタディの理論と実際』(単著,北大路書房,2007),『P-Fスタディ アセスメント要領』(単著,北大路書房,2010),『P-Fスタディ解説(2020年版)第2版』(共編著,三京房,2023)
趣味はスポーツ観戦,落語鑑賞
安井知己(やすい・ともき)
甲南女子大学
資格:公認心理師,臨床心理士