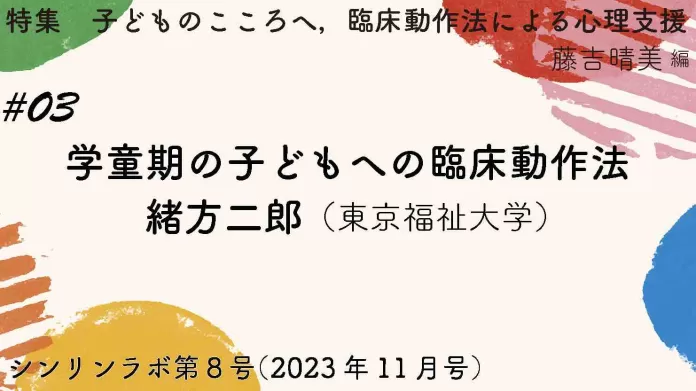緒方二郎(東京福祉大学)
シンリンラボ 第8号(2023年11月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.8 (2023, Nov.)
はじめに
本稿では,まず学童期の特徴について解説し,体験治療論(成瀬,2016)の立場から子どもたちの体験について焦点を当て,論述した。その上で臨床動作法を適用する意義や子どもたちの動作にどのような不調が見られるかを概観し,心理支援で用いられる動作課題について紹介した。最後に動画を通して学童期の子どもへの臨床動作法の実際について論じた。
1.学童期の子どもたち
1)学童期の特徴
学童期における最大の特徴は,生活する場が家庭から小学校に移る環境の変化にある。小学校では多様な友達と共に過ごし,競争をしたり,支え合ったり,主張し合ったり,戸惑ったり,妥協したりといった場面が多く見られるようになる。授業中は,説明をよく聞いて,ことばで答え,抽象的に物事を捉える機会が増えていく。また先生からは事あるごとに評価を受け,周りの友達の成績を目の当たりにし,時に劣等感を抱く年頃である。小学校は社会に出るために必要な経験を積み重ねる場であるともいえよう。またこの頃は心身の発達が著しい時期である。低学年ではまだからだの成長は緩やかだが,運動をする機会が徐々に増えることもあって,活動量は増加していく。高学年になると第二次性徴が発現し,身長や筋肉,手足の成長が著しくなる。
2)主体的にからだを動かすことの積み重ねが自己努力・自己調整力を育む
このように学童期の子どもたちは外界や内界のさまざまな要求に応えつつ,自己努力・自己調整をしながら,主体的に世界を捉え,探索的にアクティブに逞しく成長していく。この自己努力・自己調整力が心理的な自立へと繋がり,社会に出るための基盤になっていくと考える。しかしことばを用いた指導,いわゆる論理的・抽象的なやり取りや知的理解だけで,これらの力を伸ばしていくことは難しい。子どもたちは成長していく中で,ことばを覚え,からだを動かしながら,さまざまな体験をし,経験を身につけて,工夫・創造の力を伸ばしてきた。活き活きと躍動するからだを通した実感的な体験の積み重ねが,子どもたちの自己努力・自己調整力を培ってきたのである。
3)体験の内容と体験の仕方
学童期の子どもたちは内外の要求に応えるために,大人が思っている以上に考え,それぞれでからだを動かし,主体的・能動的に活動し,状況を変化させ,適応しようと努力している。からだを主体的に動かし,動く現象を動作(成瀬,2016)とすれば,動作を遂行する努力の過程の中で子どもたちはさまざまな体験をしている。
成瀬(2016)は,「人間関係や事象・状況の認知や考え,行動,ことばやイメージ,ある事象・状況,その場の問題などが内容,それに対して,好き・嫌い,喜怒の感じ方とが一体的なものとして経験されたものが体験である」としている。さらに「何々について(内容)をどのように感じるか(様式,感じ方,仕方)を分けて治療的に取り扱おうとする考え方が体験治療論である」と述べている。この立場で考えれば,子どもたちの体験は,体験の内容と体験の仕方に分けられる。例えば,「あの先生は厳しい(体験の内容)な。ドキドキするな。緊張するな(体験の仕方)」というように子どもたちの体験の実態を2つの側面から把握できる。体験の内容は主にことばで語られることが多く,体験の仕方はその内容の感じ方であり,緊張感である。
子どもたちはこれまでさまざまな体験をする中で,からだを動かしながら,状況に対応し,試行錯誤しながら適応する術を身につけてきた。身をもって体験し,実感を伴った経験の積み重ねをすることが,現実への適応をより確実なものとする。その際「あの先生は厳しい」という人物に対する認知・認識といった知的活動よりも,実感的に感じられる「ドキドキする。緊張するな」という感じ方,つまり体験の仕方から,自分がどのように対応すればいいか,どう乗り越えていくかといった手がかりを得て,自己努力・自己調整力を発揮させながら,適応に向けて努力していくのである。
4)体験の仕方が変われば動作が変わる
子どもたちは日々の生活の中で,問題に直面したとき,その物事に耐えられるよう,それ相応の緊張感を抱きながら対応している。その緊張感は自分でからだに力を入れて,緊張しているから感じているものである。問題が大きければ大きいほど,対処しようと緊張感を強くする。
ようやく問題が解決した後に,緊張感や緊張が充分に解消されれば良いが,長引き,留まり続けた上,すぐに次の物事への対処に当たるといったことが生活上あり得る。持続する緊張感は,徐々に子どもたちの自己努力・自己調整力を発揮させることを阻害し,物事の捉え方を歪め,不安や怖れを強め,柔軟な対応をできなくさせ,時に不適応に至らしめる。
また緊張は,からだのあちこちで蓄積し,徐々に習慣化し,慢性化する。からだを真っ直ぐにする力が入らず,腰周りや肩周りに反・屈の力が常態化すれば,動作が不自由になる。
臨床動作法ではからだの緊張を弛め,自由に柔軟に動かせるようになることを目指すが,そのためには動かしている本人の体験の仕方が変わらなければならない。からだを動かしていく中で,居坐る強い緊張に当たった時,自分がそれをどう処理・対応しようとしているかをまずは感じる必要がある。無意識的に避けるように動かしたり,力を抜いたり,または力を過剰に入れたりするなど,随所に主体者の不適切な体験の仕方が現れる。自らの体験の仕方を感じながら,無意識的な抵抗を抑え,意識的に緊張を弛め,適切なコースに沿って動かすように自己処理することを繰り返すと,殊更意識せずにからだを動かせるようになる。
このように体験の仕方が変容することで,動作が自由化する。その過程の中で自己努力・自己調整力が活性化し,冷静に物事を捉え,不安や怖れに動じることなく,柔軟に対応ができ,適切な現実適応ができるようになる。
2.学童期の子どもたちに臨床動作法を適用する意義
学童期の子どもたちの動作についてまとめる。
- 子どもたちは動作を通してさまざまな体験をし,経験を積み重ねていること。
- 体験し,経験を積み重ねることで自己努力・自己調整力を育んでいること。
- 体験の仕方から対応の手掛かりを得て,適応に向けて努力していること。
- 体験の仕方が不適切であれば,現実適応が困難となる。体験の仕方が変われば,動作が変わる。変えていく過程の中で自己努力・自己調整力が活性化する。
これらを踏まえれば,臨床動作法は,動作を遂行する努力活動の中で,からだの緊張を弛め,適応的な体験の仕方に変容させ,自己努力・自己調整力を活性化させることができるため,学童期の子どもたちに適用する意義がある。
3.学童期の子どもたちの不適応とからだの不調
1)学童期における不適応
学童期は集団生活に適応できるかという問題が表面に出てくることが多いが,発達障害やいじめ,対人トラブルなど心理臨床的な訴えは多岐に渡る。子どもたちはうまくいかないことへのもどかしさや不安,焦燥感などを解消しようと時に親に反抗し,お友達に手を挙げたり,物に当たったり,ひたすら抑え,我慢をすることも見られる。もしそれがいつまでも解消されないとすれば,不安や悩みを抱え,不安定で怒りやすく,内向きになり,学習意欲もなくなり,友人関係もうまくいかなくなるなど徐々に心理的な問題が表出し,常態化して本人を苦しめるようになる。
2)子どもたちのからだの不調・不具合
成瀬(2014)は,「持続的に不安や不満,怖れや怒りなどに悩まされ,対人関係や社会関係,文化への対応などこころに適応上の問題や困難などがあり,それが持続しているような場合は,からだのどこかに必ず何らかの不調・不具合が見られる」と述べている。それは子どもたちとて例外ではない。
学校生活や家庭で具体的に観察できるからだの不調・不具合といえば姿勢の歪みがある。椅子に坐っている姿勢では,顎が上がっていたり,背中が屈がっていたり,椅子や机にもたれかかったり,足を横に出したり,足を組んだり,頬杖をついていたりする。立位姿勢では,どちらかの足に重心を乗せていたり,腰が反っていたり猫背になっていたり,O脚になっていたりする。子どもたちの姿勢の特徴やからだの変化は,子ども自身が徐々に作り上げたものである。日々の生活における体験の仕方が不適切であるがゆえに,誤った力の入れ方が習慣化,慢性化しているので,からだに歪みが生じているのである。
3)姿勢を直す,緊張を弛めるのは手段であって目的ではない
子どもたちのからだは,歪みはあっても大人のように凝りがあって硬く不自由で動かすと強い痛みがあるというわけではない。多少の慢性化した緊張があっても,動かすとすぐに弛んでいくことが多い。むしろからだの動かし方が大雑把で唐突,過剰であったりするなど,安定して力を維持・調整できないことの方が多い。重要なのは,ただ姿勢を直す,緊張を弛めるということだけではなく,からだを動かしている本人の主体的な努力活動をいかに変化させ,その過程において,これまでの体験の仕方をどのように変容させるか,である。
成瀬(2014)は,「個々のからだの不調が,実は動作というひと纏まりのシステム内の緊張・動きの中のそれぞれ一部分として相互に関連し合っているので,そのうちの一つが変われば全体が変化するという傾向がある」と述べている。さらに「主要なものいくつかを意識的に自由・柔軟な動作へ変えられれば,システムが全体として新しいものになると同時に,気持ちも安定して前向きで明るく,自由で積極的,創造的になる」と続けている。この変容のためには,緊張を弛め,動かせるようになること。さらに大雑把で唐突,過剰な力を入れる動作ではなく,注意集中し,からだの動いている感じ,動かしている感じを感じながら見通しを持って遂行していく動作の在り方,体験の仕方が求められる。
4.臨床動作法を実施する際の工夫
学童期の子どもたちに臨床動作法を実施する場合,まずは楽しく行うことが大切だと思う。初めてで緊張しており,ことばのやり取りをさせられると身構えているかもしれない。また本人もよくわからないまま連れてこられたといったケースもあるかもしれない。そういう場合は,最初から形式的な援助に終始するのではなく,からだを動かすという意外性を楽しんでもらいながら,セッションを展開することも一つの方法である。
心理不適応を抱えている子どもは,評価を気にしたり,できなかったことで嫌になったり,課題に向き合えなかったり,すぐに集中力が切れてしまったりする。慣れるまでは援助者が一緒になって課題を行い,導入をスムーズにしても良い。
1回のセッションにつき30分から45分程度の枠で実施することが多いが,長い時間をかけることが良いというわけでなく,20分程度の短い時間で1つの課題を集中して行う時間を取ったりと,メリハリをつけるのも効果的である。
5.学童期の子どもへの臨床動作法の実際──動画の解説を通して──
ここでは動画の解説を通して学童期の子どもへの臨床動作法の実際を紹介する。30分程度の援助を行い,そのうちの一部を1分にまとめて編集した。
1)姿勢の特徴とからだの動かし方
動画の男児(以下,A)の姿勢は,腰が後傾し,背中を丸くして坐っている。頸の後ろ側を折るようにして,顔を前に向けている。Aがどのようなからだの動かし方をするのか見立てるために,前屈を行ってもらったところ,勢いをつけてからだを動かし,上体を深く屈げることができている。
2)努力の仕方を推測し,どのような体験が必要かを見立てる
ここで把握しておきたいのは,Aの努力の仕方である。Aは上体を深く屈げることはできているものの,自分のからだの感じやからだが動いている感じ,動かしている感じにあまり注意を向けずに動作を遂行していることが推測できる。そこで動作課題を通して,注意集中し動作をコントロールする体験,自分のからだに向き合う体験などを獲得できれば彼の体験の仕方をより適応的に変化させられるのではないかと仮説を立てた。坐骨を床にしっかりつけ,腰を立て,Aが真っ直ぐに坐れるようになることを目標にした。以下から〈〉は援助者の発言である。
3)胡坐坐位・前屈げ
真っ直ぐの姿勢を維持したまま股関節から上体を前に屈げていく課題である。やや前に上体を傾けてみる。〈真っ直ぐの姿勢を意識したままゆっくりと股関節からからだを前に屈げていきます〉と声掛けした。これは最初の前屈のような努力の仕方で遂行する課題ではないことを共有し,新たな感じを体験できるようになることを意図している。Aは集中して取り組んでいる。この後は,真っ直ぐの姿勢のまま額を床につけるぐらいまで,自分で股関節から深く上体を屈げていけるように援助していく。
4)胡坐坐位・右前屈げ,左前屈げ
左右に前屈をする課題である。この時に注意するのは,腰(骨盤)をしっかりと屈げる方向に向けてから,上体を股関節から屈げることである。この時に腕は自然に前に出して良いが,腕の力を使って上体を伸ばすような動きにしないように注意する。腰周りの動かしにくさ,股関節の硬さがある場合は,〈動かしにくいところでじっと待っていると感じが変わっていくよ。待っててごらん〉と声かけする。
5)胡坐坐位・左右のバランス取り
この課題は坐位での左右のバランス取りである。左右のお尻に均等に体重を乗せ,より安定した坐位姿勢を目指す。右のお尻に乗った時を見てみる。援助者が左に他動的に乗せた時は援助についていくように動かしている。右に乗せようとした時,途中で動きが停まってしまう。そこから他動的に乗せてみると,お尻に乗れずに上半身が右に寄りすぎてしまい,やや右後ろ後方にからだが流れた。そこで少しだけ前傾姿勢になるように援助してみる。すると踏みやすい場所を見つけたのか動揺が収まり,しっかりとお尻で踏み,からだを真っ直ぐにする力が戻ってきた。
6)セッションを終えて
臨床動作法前(図1)と後(図2)の姿勢を比べてみると,援助後は坐骨が大地についていて,腰が立ち,真っ直ぐの姿勢で楽に坐れている。注意集中し,動作をコントロールする体験,自分のからだに向き合う体験を積み重ねながら,自身のからだを真っ直ぐに位置付けることができるようになったと考える。

図1 臨床動作法を行う前

図2 臨床動作法を行なった後
文 献
- 成瀬悟策(2014)動作療法の展開―こころとからだの調和と活かし方.誠信書房.
- 成瀬悟策(2016)臨床動作法-心理療法,動作訓練,教育,健康,スポーツ,高齢者,災害に活かす動作法.誠信書房.
名前 緒方二郎(おがた・じろう)
所属 東京福祉大学
資格 博士(臨床心理学)・公認心理師・臨床心理士・臨床動作士