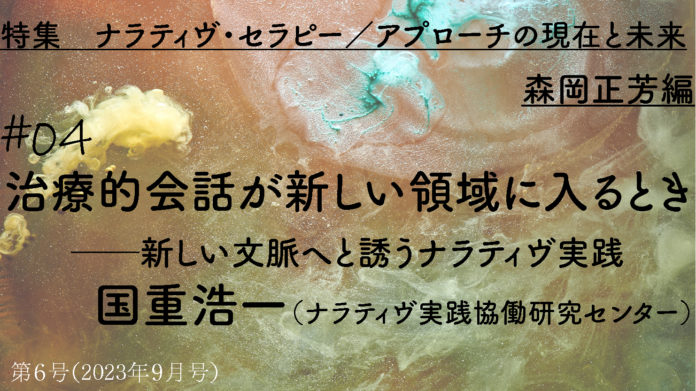国重浩一(ナラティヴ実践協働研究センター)
シンリンラボ 第6号(2023年9月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.6 (2023, Sep.)
はじめに:年季の入った「新しいもの」
原稿の依頼を受けてから,ナラティヴ・セラピーが誘っている「新しい」治療的文脈は何なのだろうかということを考えていた。手元にある書籍や論文を眺めてみると,それぞれが出版された年のことがどうしても気になる。それらは,決して新しいものではないのである。
マイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンは,1980年代からナラティヴ・セラピーの原型となるものを世に送り出し始めた。ナラティヴ・セラピーを世に知らしめた「物語としての家族」が出版されたのは,1990年のことである。さらに言えば,マイケルやデイヴィッドが拠り所にする哲学的な考察は,1960年代よりも前のものもある。ここで哲学的な考察とは,哲学だけでなく,文化人類学,社会学,民俗学,歴史学などさまざまな領域を含んでいるが,興味深いことに,あまり心理学には触れていない。
哲学的な考察は,そのままでは対人支援の領域にどのような可能性をもたらしてくれるのかについて,不透明なままである。私には,そこをつないでくれる理論家や実践家が必要となる。1980年頃より,世界のさまざまなところで,ポツポツと哲学的な考察を臨床の場に活かすための試みが世に出されていった。そして,多くの理論家や実践家がそれに刺激を受け発展させてきたのである。
ナラティヴ・セラピーのみならず,コラボレイティブ・セラピー(Anderson & Goolishian, 1988; Anderson, 1997),リフレクティング・チーム(Andersen, 1991),オープンダイアローグ(Seikkula & Arnkil, 2006)など,実際にどのような取り組みをするのかについては違いがあるものの,背後にある思想的な基盤は同じパラダイムにあると見なしてもいいのではないかと考えている(e. g. , Gilligan & Price, 1993; Malinen, Cooper, & Thomas, 2013)。これらをポスト構造主義的な,または社会構成主義的なアプローチと呼ぶことにしよう。日本では,広義のナラティヴ・アプローチと呼ばれることもあったようであるが,「ナラティヴ」という用語で他のすべてを包括させることは無理がある,と私は考えている。
このような状況から,私がナラティヴ・セラピーの話を持ち出すとき,「新しいもの」の話をしているのではない。私が『ナラティヴ・セラピーの会話術』を2013年に出版したとき,ナラティヴ・セラピーなどの本を多数翻訳している小森康永さんに「本書の出版に寄せて」を書いてもらった。その中で,小森さんは次のように述べている(国重,2013)。
「ナラティヴ」は,narrative model, narrative therapy, narrative approach, そして,narrative practiceと,その名称をくねくねと変えながら,この20年の間にひとまず完成の域に達した。(i頁)
つまり,ナラティヴ・セラピーはある程度その取り組みの方法が形になっているということである。過去によく聞いていた音楽のことを思い出してほしいのだが,80年代,90年代の音楽は懐かしいであろう。その時代のものを持ち出して,何らかの新しさを見出すこともできないわけではないが,ナラティヴ・セラピーの話を持ち出すときにしているのはそのようなことではない。ナラティヴ・セラピーが基盤としているパラダイムの話は,依然として多くの人にとっては,新しいものであり,新鮮なものにとどまっているので,新しいものとして説明せざるを得ないのである。
本稿では,ナラティヴ・セラピーのパラダイムの魅力とその難しさ,そして,ナラティヴ・セラピーを実践できるようになるためにはどのようなことが必要とされているのかについて述べてみたい。なお,文章を練りながら,必要なことを書いていったら,指定された文字制限を大幅に超えてしまった。このことは最初にお詫び申し上げておきたい。
1.ナラティヴ・セラピーのパラダイムの魅力
ナラティヴ・セラピーのみならず,ポスト構造主義または社会構成主義に基盤をおくアプローチに取り組んでいると,先人たちが積み上げてきた考察の緻密さに圧倒されつつも,倫理的にも,社会正義という視点においても妥当性を感じられ,魅力を感じていく。これは,これらのアプローチが役立つからだけではなく,それが公正なアプローチであると思えるからである。
さらに,実践も豊富に積み重ねられてきている。一対一のセラピーだけでなく,カップルや家族に対して,そしてコミュニティに対してさえ,取り組んでいるのである。このような実践は,どこかで聞いたことがあるようなものの繰り返しではなく,エキサイティングであり,プレイフルであり,問題の重大さに圧倒されることなく希望の光を見せてくれる。
人を苦しませている問題についての経緯を調べ,要因を特定し,その要因を排除するというような一般的な方法は,直線的なアプローチと見なすことができる。一方で,ポスト構造主義的なアプローチは,当然なこととしてしまっているような社会常識からの影響を探ることによって,問題を作り上げている社会文化的な側面や,それがどのように語られているのかという言語的な側面に目を向ける。
そして,問題を作り上げているのが当の本人ではなく,他に要因もあるということが判明し,自分自身もその影響を受けてしまっているのだと理解できるとき,今までの理解様式が一変し,新たな可能性を垣間見ることができるのである。
このようなプロセスは,実に不連続的で,どうしてそうなったのかさえ分からないことも多い。しかし,当の本人は,教育,アドバイス,介入という手段ではなく,比較的自然に,そしてさらに良いことに本人自身によってたどり着いたとさえ思えるのである。
このパラダイムのアプローチは,相手との会話に重点を置く。会話そのものに可能性を見出していると言えるであろう。
話し手の話を単に受け入れ,その方向性だけで話を進めようとすると,例えば,苦悩のストーリーは苦悩のストーリーだけに終始することになりがちである。このような状況に陥らないために,教育,コーチング,指導的な関わりをしたくなってしまう。
ところがナラティヴ・セラピーにおいては,苦悩のストーリーを受け取りつつも,別のストーリーへの可能性を垣間見るように誘うことができる。横山克貴さんと一緒に編集した『ナラティヴ・セラピーのダイアログ』(2020)には,ナラティヴ・セラピーのワークショップなどで行ったデモセッションの逐語を4本掲載した。逐語は,書籍化のために読みやすいようにしたものではなく,できるだけそのままの表現を載せている。この逐語を読んでもらえれば,カウンセラー側からの応答はほとんどが問いかけであり,介入らしいものはあまりないことに気づくだろう。それでも,クライアント役についてくれた人たちは,受容され,認証されたと感じ,希望らしきものを手にすることができたのである。
このように書いていくと,いったいどんな技法を使うのだろうかと思うかもしれない。しかし,ナラティヴ・セラピーでは単一の質問や技法に頼ることはない。ここにナラティヴ・セラピーの深みもあるし,難しさもある気がする。
マイケルやデイヴィッドたちの貢献によって,ナラティヴ・セラピーという領域においては本当に豊富なアイデアと質問がある。しかし,そのようなアイデアや質問を参考にしつつ,話し手の状況にあわせ,その都度,質問を仕立てていく必要があるのである。つまり,ナラティヴ・セラピーという領域においては,これまでのアプローチにはなかった斬新で魅力的な関わり方を数多く知ることができる。その一方で,いつどのタイミングで,どのような方向性の質問を投げかけていくのかということに取り組む必要があるということになる。
「リアムとペニー」
ナラティヴ・セラピーの質問に接すると,このような質問はいったいどのような視点から導き出されたのだろうかと考えずにはいられないようなものが多くある。このような質問をしても,人は答えてくれるのだろうかという不安も生じる。
当然のことながら,そのような質問を脈絡を考慮することなく唐突に投げかけても,人は答えてくれないだろう。しかし,会話の流れの中で適切な時を見出せれば,そのような質問は多大な影響をもたらす。ひとつ例を挙げてみよう。
マイケルは,『ナラティヴ実践地図』(White, 2007)の第2章「再著述する会話」において,ある事例を紹介している。登場人物は,15歳の息子のリアムとその母親のペニーである。私の中では,「リアムとペニー」の会話として記憶されている。
ペニーの夫は,非常に虐待的な男だったので,ペニーはそこから逃げ出せば,息子のリアムはよくなるだろうと考え,やっとの思いで逃げ出す。ところが,リアムは依然として「人生への希望を失いそう」で,学校に行くのをやめ,ついには自殺をほのめかすことを日記に書くようになってしまったのである。
ペニーは,かかりつけ医の助言で,マイケルに連絡をとり,マイケルのアドバイスをもらいながら,なんとかリアムと一緒にカウンセリングに来ることができた。マイケルは,些細なものに見える行為を取り上げ,その意味を尋ね,同席しているペニーの協力を得ながら,過去を探索するのである。
話の流れの中で,マイケルは,「昔からずっと,リアムは自分のことよりあなた(ペニー)のことの方を心配していた」(White, 2007/邦訳56頁)ことを知ると,ペニーに「どこからでもいいんです。リアムがあなたの人生をどれほど大切に考えているのかを示す彼の行為について,私に聴かせてもらえるストーリーがあれば,それは役に立つんです」(邦訳57頁)と伝える。
するとペニーは次のようなエピソードを語った。リアムが8歳の頃のこと。ペニーの夫は,難癖をつけて,ペニーを殴っていた。ペニーはできる限り,そのような場面をリアムに見られないようにしていた。すると,ガラスが割れる音がした。夫が殴るのをやめてリビングに行くと,誰かが石を窓の外から投げ込んだらしく,割れたガラスがカーペットに散乱していたというのである。結局,夫は犯人がリアムであることを突き止めて,リアムを鞭で打ってしまったのである。
マイケルは,このリアムが取った行動についての意味づけを共に作り上げていく。それは,「抗議」していたということであり,「勇気と公平性」をも示していたと言うことになったのである。このような意味づけを作り上げることこそ,会話の中で行われなければならず,人と話していく意義があるのだ。
リアムの人となりを示すこの重要なエピソードは,忘れ去れていたものであった。たとえ思い出せたとしても,ペニーにとっては,「暴力を隠そうとしたけど隠し通せなかった」「結局は,リアムは鞭で打たれてしまった」という物語に回収されてしまうだろう。リアムが取った行動の価値や意味,そしてペニーが子どもには見せたくなかったのだという気持ちを持っていたことの価値や意味は,なかったものとなってしまうのである。
希望に繋がる会話
先ほど述べた直線的なアプローチにおいて,「人生への希望を失いかけている」子どもとどのように話をするだろうか考えてみると,ナラティヴ・セラピーで提供しようとする会話の違いが鮮明になっていく。
まず私たちが考えてしまいそうなことは,どうして人生への希望を失っていくことになったのか,原因を探そうとするだろう。リアムとペニーにとって,このような原因の探索自体はそれほど難しいものでもなく,私たちにも当然と思えるような話をしてくれるだろう。それは,父親の虐待である。そして,多くの場合語られることになるのは,母親のペニーが子どもを守ってやることができなかったことである。そしてリアムは,私たちの前に,虐待を受けた子,もしくはかわいそうな子として映るようになる。
さて,このような会話を続けたらどこに行きつくのだろうか,と考えたことがあるだろうか? 大切なことは,リアムが「人生への希望を失いかけている」ことに対して,何らかの希望を見出すことである。
原因の話をするとき,すでに与えられてしまったダメージの話をすることになる。そのダメージを無かったことにする手立てはない。せいぜい忘れるか,気にしない,気持ちを切り替えるなどの本当にできるかできないか分からないような手段しか思いつかないときもあるだろう。虐待のようなことを忘れられる人はいない。気にしないことなんかできない。このようなことを提案されて,できなかった場合,それは,その人のエンパワーメントに繋がるのではなく,自分の気持ちをしっかりとコントロールするともできないという気持ちを抱かせてしまうことだってある。つまり,原因を探求し,それを解決するような会話は,実のところ,希望には繋がっていきにくいのである。
それよりも,虐待,機能不全,母親失格,虐待児などのストーリーが覆い隠してしまったストーリーを探索し,今後生きていく上で大切なストーリーが他になかったのかを探すことの方が,より希望に繋がるというわけである。
私が学んだ大学院のチームが書いた書籍には,「希望を掘りあてる考古学」とサブタイトルが記されている(Monk et al., 1997)。ナラティヴ・セラピーでは,希望に繋がるような会話とはどのようなことなのかについて,綿密に検討されている。人と関わるときに,希望に繋がる会話へのヒントが多くあるのだと聞けば,多くの人は興味を持ってくれるだろうか? 私がナラティヴ・セラピーに取り組み続けることができた最大の理由は,ここにある。
2.ナラティヴ・セラピーのパラダイムに向かうために
できることなら,このようなアプローチを多く人に知ってもらい,活用してもらいたいと思う。ところが,なぜかそのようになっていないのである。この傾向は,日本だけのものではない。日本よりはナラティヴ・セラピーの実践家がいるとは思うが,北米でもニュージーランドでも,同じである。ニュージーランドでは,大学のカリキュラムでナラティヴ・セラピーを教えているところは多い。毎年,何十名という人がナラティヴ・セラピーからのアイデアを片手に世に出ていく。ところが,多くのものがナラティヴ・セラピーのアイデアにとどまることはないようである。
これは,当然のことながら認知行動療法というエビデンスがあるとされているものを重用される動きと無縁ではない。多くの組織が認知行動療法をベースにしようとしているし,医師からも認知行動療法でするようにと依頼が出されるようになっている。日本もこの世界的な動きに追従するであろうことは,容易に想像ができる。
それでも,小森康永さんや奥野光さんたちがこれだけの量のナラティヴ・セラピーに関する文献を訳してくれているのだから,実践が広がるのではないかと思うのだが,そうなっていないところを見ると,どのような要因が作用しているのか検討する必要がありそうである。つまり,問われるべきことは,「なぜナラティヴ・セラピーの実践が広がらないのだろうか」,「どのように今までとは違った方法でナラティヴ・セラピーを示すことができるだろうか」ということであろう。
以下,いくつか思いつくことについて書いてみたい。
カウンセリングの会話そのもの
2000年前後にニュージーランドにあるワイカト大学で,ナラティヴ・セラピーを学んで以来,私は臨床だけに取り組んできた。研究機関に属し,学術的論文を発表したこともない。学会で事例を発表したことぐらいはある。ただ,バーナード紫さんという,私と同じニュージーランドの町に住み,英語を専門としながらも,ナラティヴ・セラピーの大学院で学んだ人と出会うことができたので,一緒に細々と文献の翻訳には取り組んできた。
2014年に,日本吃音臨床研究会の伊藤伸二さんがナラティヴ・セラピーについて,2泊3日のワークショップ講師として招いてくれるまで,ナラティヴ・セラピーを人に教えたこともなかった。
ところがこの後,ナラティヴ・セラピーを人に伝える機会をもらえるようになり,私の周りにナラティヴ・セラピーに真剣に取り組んでくれる人たちも増えていった。そして,ナラティヴ・セラピーを専門とするナラティヴ実践協働研究センターをクラウドファンディングによって立ち上げることもできた。
ナラティヴ・セラピーの文献はそれほど読みやすいものでもなく,読んだからといってすぐに実践できるようなものではない。それでも,そのような難解さを乗り越えて,ナラティヴ・セラピーに取り組んでいる人が増えているのはどうしてなのだろうかと考えることがある。
研修講師の依頼を受けてから,私は心に決めたことがひとつある。それは,ふだん自分がしているカウンセリングの会話を見てもらおうということであった。これは,ナラティヴ・セラピーの技法を見せるためのものではなく,話し手の状況にあわせながら会話をするということである。つまり,ナラティヴ・セラピーの技法を見せるためのデモンストレーションはしないと決めたのだ。そうはいっても,ナラティヴ・セラピーしか学んだことのない私は,このアプローチをベースにして会話を進めるしかないので,わざとらしく見せようとしなくても,ナラティヴの風味は出てくるだろうとも思ったのである。
人にナラティヴ・セラピーを伝え始めた頃は,自分の伝え方に自信を持てるわけはないので,受講者にどうだったのかを聞いていった。(今でも気になる点ではあるが)特に印象に残ったところはどこでしょうか,と。事前に準備をしてスライドを用意しナラティヴ・セラピーについて語ったのだが,多くの人が伝えてくれたことは,カウンセリングのデモンストレーションが印象に残ったということだった。
私の親しい知人は,臨床心理学を大学院で学んだときに,相手と会話をすることで何か違いをもたらすことができるとは思わせてもらえなかったと教えてくれた。つまり,カウンセリングの肝である会話の意義を実感させてもらえなかったのであろう。
ところが,ナラティヴ・セラピーを基盤としたデモンストレーションにおいて,話し手はより生き生きと語り出し,大切なことに気づき,将来に対して違ったように取り組めるところまでたどり着けることがあったのである。
新しい認識論を持つことの難しさ
そして,最も難しいハードルについて考えてみたい。それは,ポスト構造主義や社会構成主義が提示するものの見方を身につけていくことである。
ポスト構造主義や社会構成主義が示す基本的な考え方自体は,シンプルである。ガーゲンらは次のように述べる。
私たちたちが「現実だ」と思っていることはすべて「社会的に構成されたもの」です。もっとドラマチックに表現するとしたら,そこにいる人たちが「そうだ」と「合意」して初めて,それは「リアルになる」のです。(Gergen & Gergen, 2004/20頁)
ところが,このようなシンプルな考え方を,さまざまなことに当てはめて考えようとすると,「突如としてシンプルさは消えてしまうのです。この基本的な考えは,私たちが世界や自分について教わってきたことのすべてをもう一度考え直すことを促します」(Gergen & Gergen, 2004/邦訳16頁)とあるように,自分でいろいろと考えていく必要がある。
ここは特に重要な点である。ポスト構造主義や社会構成主義の原則的な説明は,なるほどそのようなものかもしれないと読める。難しい文章も多々あるが,要約してシンプルに伝えることもできるので,読み手はその内容を理解できるだろう。ところが,そのような原則的な説明が,私たちが学んできたことや,ものの見方にどのように影響するのかについて考え始めると,どのように考えたらいいのかさえ分からなくなってしまうことがある。いったいものごとをどのように見たらいいというのか,今まで学んできたことはどうなるのか,見通しが立たないところに置かれてしまうのである。
ポスト構造主義や社会構成主義では,私たちが真実である,本当である,当たり前であるとしているものに対して,それは間違っており,別の正解があるのだということを述べているのでは決してない。それは,他の見方や理解の仕方がたくさんあるのだということを示唆しているのである。そのため,ポスト構造主義や社会構成主義によって,よりよい真実や正解を手にすることはできない。このような考え方に正解や真実を求めようとするのであれば,「正解を求めるその姿勢」から見直すように求められているということである。
正解や真実を求めようとする人は,マーティン・ペインが述べるように,居心地の悪さを感じることであろう。
より具体的にいえば,この思想は,ほとんどすべてのものについて,究極的な確実性など決してあり得ない,という居心地の悪い課題を突きつけているのです。(Payne, 2006)
必要とされる触媒
ナラティヴ・セラピーがある程度の形になってからは,ナラティヴ・セラピーの概要について説明する文章は,ある程度同じようなものである。私もいつも同じようなことを書いているような気がしている。原稿料をもらうからには何か目新しいこと書いてみようとするのだが,だいたい同じようなこと書いているか,すでに他の誰かが書いたものをなぞっているだけのような気がしてならない。
さまざまな領域におけるナラティヴ・セラピーの取り組みについては,読み応えもあり,いろいろな気づきをもらえるのではあるが,イントロダクション的な説明については,すでに出版されている書籍や論文で十分に知ることができる。しかしそれだけでは,広がっていっていないし,実践に繋がっていないように見受けられる。よって,そこには,何かしら「触媒」となるものが必要なのだと思う。
私は,先に述べた実際の会話のやりとりを見ることに加えて,書いてあることがいったい何を意味しているのか,すでに知っていることをどのように考え直すように促しているのかについて,誰かと「語り合う」機会を持つということが大切になるのではないかと考えている。
ナラティヴ実践協働研究センターにおいて,ナラティヴ・セラピーについてのワークショップを開催しているが,その中心となるものは,提供された知識をどのように理解し,意味を見出したのかについて,グループで話し合うものである。このプロセスによって,ナラティヴ・セラピーがより身近なものとなり,実践につなげることができるようになってきている人は少なくない。
それでも,このような語り合いの場においてでも,自分が当然としてしまっていることに気づき,他の見方もあるのだということに気づくことは容易ではない。
例えば,専門的なものではなくとも,人との関わりの中で,相手の様子を観察したり,語りを聞いて,問題の本質や原因,またはその人の本質や問題が明確に見えたと思えるときがある。その時に,私たちはそのことを相手に伝えたくなる衝動に駆られる。そして,人の話が聞けなくなり,いつ自分の気づきを共有できるのだろうかとばかり考えるようになる。だれでも,そのような気づきを共有されたこともあるだろうし,そのような気づきを共有したこともあるだろう。
ポスト構造主義や社会構成主義では,そのような明確で直線的な説明に対して,私たちに注意を促している。そのような説明以外の理解様式が必ずあるのであるのだが,一つの直線的な説明しか目に入らなくなってしまっているのだ。そのときこそ,人と対話しなければならないのである。
自分が手にしている確実な説明を一つひとつ検証して,必要であれば手放すこと,これが求められていることなのだろう。ところが,自分が学習しながら積み上げてきたことを,このように検証することは,マーティン・ペインが言うように実に居心地の悪いことでもある。
このようなプロセスを,アンラーニングとも呼ぶ。アンラーニングを日本語に意訳するとすれば,「学んだことをほぐしていく」ことである。ほぐしていくこととは,今まで学んできたことを否定することでも,忘れることでもない。今まで学んできたことは,大切なことである。しかし,それを絶対視しない姿勢が求められるということである。ニュージーランドでナラティヴ・セラピーを実践しているゲイル・チェルは,知識や学んだことをしっかり握りしめているのではなく,そのようなことをゆるく保持する姿勢が必要だと述べる。
さいごに
ナラティヴ・セラピーが基盤としているパラダイムを実践につなげていくために,二つの触媒を検討してきた。一つは,実際のカウンセリングの会話を見ることである。もう一つは,さまざまな学術的な領域で学ぶべきものとなってきているポスト構造主義や社会構成主義,そしてナラティヴ・セラピーについて読み,それが自分の見方や考え方についてどのように考え直すように示唆しているのかについて対話していくことである。
ここで,私がワークショップのなどで何度も引用している言葉を紹介したい。これは,トム・アンデルセンが,ハロルド(ハリー)・グーリシャンの言葉を紹介しているという形を取ってる。トムは,自身も何度もこの言葉を引用している。それほど重要視していたのであろう。
ハリー・グーリシャンがとても熱心に言っていたことだが,「僕らは,自分が考えていることを言ってみないことには,それが何かわからない」ということだ。彼は言った。「考えることを見つけるためには,話し続けなければならない」。表現が先で,それから意味が生じる。(Malinen, Cooper, & Thomas, 2013/邦訳75頁)
ここまで述べたように,対話すべきことというのは,私たちがあまりにも当然のこととしまっていること,あまりにも明白に見えることである。このようなことについて語り合うことは,それほど容易なことではない。
対人支援の場で,クライアントがあまりにも凝り固まった考えによって,苦悩を作り上げているのではないかと思えるような場面に遭遇することは珍しくない。何とかして,そのような考えを変えてほしいと願うことがあるだろう。
まずは,相手にそれを求める前に,自分が当然としてしまっていることをほぐしてみることは,その大変さも理解できると共に,それが可能なものであった場合には,相手が考えを変える取り組みによりしっかりと付き合えるようになるかもしれない,と私は考えている。
公平な立場に身を置くためには,私たち自身が異なる意味や意見をこころに抱いてみるという,いわばリスクを覚悟しなければならない。クライエントにそれまでの古い考えから離れてほしいと私たちが願うように,私たちセラピストも自らの古い考えから出て行かなくてはならない。自分も変化するというリスクを冒すことによってのみ,お互いを認め合える会話,つまり対話は,新たな展開を見せてくれるのだから。(Anderson & Goolishian, 1998/邦訳73頁)
文 献
- Andersen, T. (1991)The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues. W. W. Norton. (鈴木浩二訳(2015)リフレクティング・プロセス―会話における会話と会話(新装版).金剛出版.)
- Anderson, H. (1997)Conversation, Language, And Possibilities: A Postmodern Approach To Therapy. Basic Books. (野村直樹・吉川悟・青木義子訳(2001)会話・言語・そして可能性―コラボレイティヴとは? セラピーとは? .金剛出版.)
- Anderson, H & Goolishian, H. (1998)Human Systems as Linguistic Systems: Preilminary and Evolving Ideas about the Implications for Clinical Theory. Family Process. 27(4): 371-393. (言語システムとしてのヒューマンシステム.In: 野村直樹訳(2013)協働するナラティヴ.遠見書房.)
- Gilligan, S. & Price, R. (eds.)(1993)Therapeutic Conversations. W. W. Norton.
- 国重浩一(2013)ナラティヴ・セラピーの会話術:ディスコースとエイジェンシーという視点.金子書房.
- 国重浩一・横山克貴(編)(2020)ナラティヴ・セラピーのダイアログ:他者と紡ぐ治療的会話,その〈言語〉を求めて.北大路書房.
- Malinen, T. , Cooper, S. J. , & Thomas, F. N. (2013)Masters of Narrative and Collaborative Therapies: The Voices of Andersen, Anderson, and White. Routledge. (小森康永・奥野光・矢原隆行訳(2015)会話・協働・ナラティヴ―アンデルセン・アンダーソン・ホワイトのワークショップ.金剛出版.)
- Monk, G. , Winslade, J. , Crocket, K. , & Epston, D. (eds). (1997) Narrative Therapy in Practice: The Archaeology of Hope. Jossey-Bass. (国重浩一・バーナード紫訳(2008)ナラティヴ・アプローチの理論から実践まで─希望を掘りあてる考古学.北大路書房.)
- Jaakko Seikkula, J. & Arnkil, T. E. (2006)Dialogical Meetings in Social Networks(The Systemic Thinking and Practice Series). Routledge. (高木俊介・岡田愛訳(2016)オープンダイアローグ.日本評論社.)
画像
国重浩一(くにしげ・こういち)
所属:ナラティヴ実践協働研究センター
資格:臨床心理士・ニュージーランド・カウンセラー協会員
主な著書:『ナラティヴ・セラピーの会話術』(金子書房,2013)『震災被災地で心理援助職に何ができるのか?』(ratik,2014)『どもる子どもとの対話』(金子書房,2018)『ナラティヴ・セラピーのダイアログ』(北大路書房,2020)『ナラティヴ・セラピー・ワークショップ Book Ⅰ&Ⅱ』(北大路書房,2021&2022)『もう一度カウンセリング入門』(日本評論社,2021)など。
主な翻訳書:『ナラティヴ・アプローチの理論から実践まで』(北大路書房,2008)『ナラティヴ・メディエーション』(北大路書房,2010)『心理援助職のためのスーパービジョン』(北大路書房,2012)『カップル・カウンセリング入門』(北大路書房,2022)『ナラティヴ・セラピー入門』(北大路書房,2023年)など。