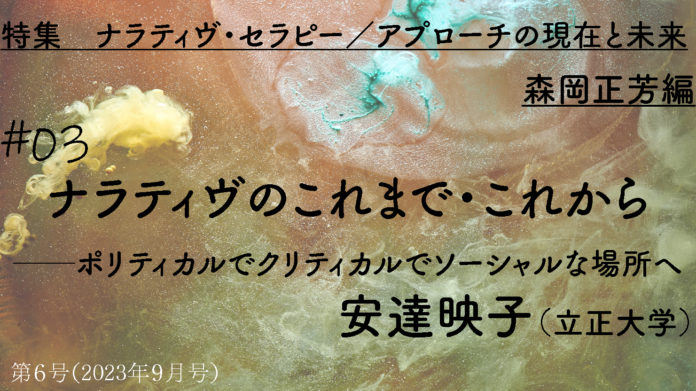安達映子(立正大学)
シンリンラボ 第6号(2023年9月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.6 (2023, Sep.)
理論紹介がはじまってから30年がたつ日本のナラティヴ・セラピーも,実践としてはマイナーレーベルのまま時が流れた。目立たず地味にコツコツとやっていくのは心許ないものの,「わかる人にはわかる/わかればよい」というある種の気楽さもある。ナラティヴに関心をもつ人が増えるのは支えになる一方で,その気楽さをどこか手放すことでもあった。多くのことがそうであるように,広まるときにはカド(それが決定的に重要な「尖り」だとしても)がとれ,「わかりやすさ」が好まれる。ナラティヴも,支持が集まるときには口当たり良くマイルドになる。それを歓迎するかどうかは,立つ場所によって変わる。
ナラティヴ・アプローチのなかでもナラティヴ・セラピーは,〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉な実践である。そうキッパリ言ってみることから,この文章をはじめてみよう。それなのになぜ,〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉なその側面はこぼれ落ちてしまうのだろう。それをどう手繰り寄せ,スタンスとして共有できるだろう。ナラティヴのこれまで・これからをめぐって置いてみたいのは,この問いだ。
あくまで日本における,ナラティヴのこれまで
ナラティヴ・アプローチとナラティヴ・セラピーは,2023年の現段階においては,ことばの使用を明確に分けたほうがよいという気がしている。ナラティヴ・アプローチとは,物語という形式において人々が意味を生きる存在であることに関心をよせ,何らかの事象に迫り取り組もうとする立場の総称である。一方,ナラティヴ・セラピーはその一角を占めつつも,ホワイトとエプストンが切り拓いてきた思索と実践およびその後継を狭く指している。
両者を分けるべきだと考えたのは,わたし自身の反省からでもある。「ナラティヴのこれまで・これから」を考えるにあたり,自分が書いてきた論文を見返してギョッとしたのだ。どう考えてもナラティヴ・セラピーの実践や研究報告であるはずのものに,使用されている表記はすべてナラティヴ・アプローチになっていた。社会福祉学系の学術誌に「セラピー」の語を使うのはカドがたつと忖度し「アプローチ」でマイルド化した気配が濃厚。しかもそれをすっかり忘れていた無自覚さ,というおまけ付きに愕然としたわけだ。
そう二つを区別した上で,ナラティヴということばが対人支援領域に散見するようになった日本のこの30年のナラティヴ・アプローチをあらためて見渡すなら,やはりこの3つの系譜を押さえておくのがわかりやすいように思う。
①ナラティヴ・セラピーをはじめ社会構成主義を前提とする「ナラティヴ&コラボレイティヴ」
(かつて日本では,この全体が広義のナラティヴ・セラピーと呼ばれてもいた)
②医療人類学の「病いのナラティヴ」
③医療における「ナラティブ・ベイスト・メディスン/ナラティブ・メディスン」
英語圏では日常語である「ナラティヴ」は,日本でもそれ以前から言語学領域や文学研究においてタームとして存在していた。だが,ナラティヴがそれとは少し別な角度から注目されていく背景には,ポスト構造主義/ポストモダニズム,あるいは社会構成主義という認識論的立場への移行とそこに通底する言語論的転回をどうしても見ておく必要がある。所与の事象や出来事が言語という手段によって語られるのではなく,言語的相互行為が事象や出来事をその都度意味ある現実として立ち上げるのだという転回が,語り(telling)とその産物としての物語(story)の双方を含意するナラティヴの再発見にもつながった。この点は,ナラティヴ・アプローチ全体の前提としても依然として重要だろう。
とはいえ,社会構成主義との距離感はさまざまで,ナラティヴという語を使うことで何を意図し,強調したいかは立場によって違いもある。例えば,社会構成主義に徹するナラティヴ・セラピーにとって,〈エビデンス〉は社会において説得力をもち公認されやすい語り方,すなわち一つのナラティヴにすぎないけれど,ナラティブ・ベイスト・メディスンにおいては,〈ナラティブとエビデンス〉が対称されるというゆらぎが残る。「ヴ」VS「ブ」は単純な表記問題にみえて,narrativeというワードのもつ拡がりと豊かさから何を汲み取りたいのかをめぐる差異を透かしもする。
ナラティヴ&コラボレイティヴの動向を核にしたナラティヴ・アプローチの包括的検討や議論は野口裕二らによってなされてきたし,心理学の立場からは森岡正芳による貴重なコミットメントが持続されてもきた。ナラティヴ・セラピーについては,ホワイトの著作をはじめ多数の原著が小森康永らによって精力的に翻訳され,江口重幸らによる医療人類学,斎藤清二らのナラティブ・ベイスト・メディスン等についても紹介が進んだのが2010年くらいまでの時期だっただろうか。
これら理論的産物を下敷きにして,わたしたちが学べる環境はかなり整っていた。けれどもこの時点では,広範な熟議が育ち,後押しされて実践が大いに展開するという動きにまでは至らなかった。当初にあった熱は,完全に冷めたわけではないとしても,上がり切らずに緩やかになったような感覚がある。ただ,言いかえれば,ナラティヴをめぐる地熱のようなものは保たれた。この事実はかなり重要だったかもしれない,と今にして思う。
〈ナラティヴとケア〉の文脈,あるいはそこからこぼれるもの
潮目が少し変わり,こうした土壌とはまた別な地点からナラティヴに向けられる眼差しが温度を取り戻しはじめたのは2015~6年頃だったと記憶する。契機となる直接的で具体的ないくつかの事柄も思い浮かぶのだが,むしろここで書いておきたいのは,ナラティヴ再浮上を裏側で支えたかもしれない社会的文脈のことだ。
ナラティヴの30年とは,実はそのままズバリ,バブル崩壊とその後の「失われた時代」を指している。いうまでもなく日本においてこの30年は,成長どころか停滞ないしは後退が恒常化した時期である。グローバリゼーションに構造的に対応しきれないところが雇用形態で調整され,ICTの動向がそこに重なりながら,家族形成や人間関係のあり方も大きく影響を受けた。格差と分断,個人化が進行し,困難への対処に自己責任が求められる包摂性を切り詰めた時代。そうしたなかで,人々の疲弊や孤立や不調,あるいは「生きづらさ」は,語られるべきものとしていつ溢れ出してもおかしくないかたちで堆積していたはずだ。あるいは,こうも言えるかもしれない。そうしたナラティヴが「ケア」を待たれていた,と。
遠見書房『N:ナラティヴとケア』が年1回の刊行でスタートしたのは2010年である。誌名が『ナラティヴとケア』となった経緯や事情はまったく知らないのだが,こうした時代背景のなかで行為や場として現に要請され,かつ「刺さる」ことばの一つに「ケア」があったことは腑に落ちる。「ケア」へのニーズと希求は,個人と社会に通底して存在し始めていた。それと連動するように,「ケア」をめぐる哲学的思索などへの関心も広がりつつあった。
ナラティヴの地熱期に,ナラティヴとの関係を深めていたのは看護領域である。重要性を増し多様性への配慮を求められるようになった「ケア」の最前線である看護が,その角度からナラティヴに着目するのは,自然な流れに思える。「ケア」する実践にとって,ナラティヴは探求の余地をたっぷりはらんだ,豊かな土壌に映って不思議はない。
とはいうものの,わたしの関心はそれ自体とは別なものにも向かう。〈ナラティヴとケア〉が結びつくことで,逆に見失われていくものは何か,ということだ。
丁寧に議論すべきところを端折っていえば,〈ナラティヴとケア〉の結びつきがクローズアップするのは,〈一人ひとりの語りに寄り添う〉とか〈あなたの物語を大切にする〉というタイプのナラティヴの「語り方」である。それを切実に求める文脈──傷んだ個人としてモナド化したあなたやわたしが生きる社会──がこの間あったのは,すでにふれたとおりである。この文脈のなかでナラティヴは,そうした人々の苦境を解き,再価値化するための救済ワードとして光が当たる。ナラティヴが再浮上していく背景には,社会全体が停滞する一方で自己責任追及や自己批難の声に追い立てられバラバラになるわたしたちが,語り聴くというつながりのなかで回復し,再生されるかもしれないということへの切望や期待がありはしなかっただろうか。
しかしながら,こうした〈ナラティヴとケア〉的ないし「寄り添い系」スタンスや取り組みは,どうしても個人あるいはケアされる人とケアする人との,いわば狭い関係性へと焦点を切り詰めがちである。本来その苦境や生き難さと無縁でないはずのより大きな文脈や社会の構造的側面は,このとき視界から遠のく。〈ナラティヴとケア〉が連合体となって,極端にいえば個人や個別の関係救済的な自己対処が志向されてしまうとき,社会的文脈や構造への問題意識はこぼれ落ち,棚上げされてしまいかねない。
寄り添い,救済し,癒すナラティヴ・アプローチがあること,あってよいことは否定しようもない。ただ,ナラティヴ・セラピーはその方向とはちょっと別物です,ということは強調したくなる。問題を人々の内側にとどめて理解することから離れ,あくまで文脈との接続において〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉に探求すること。ナラティヴ・セラピーはこっちなんです,ということなのである。
〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉なナラティヴ・セラピー
ホワイトとエプストンの関心は,つねに問題をとりまく社会政治的文脈(sociopolitical context)に向けられてきた。彼らが構想し,実践してきたナラティヴ・セラピーとは,「人間の問題をより広い生活の文脈のなかで,たとえば家族のなかで,社会のさまざまな諸機関の中で,ローカルな文化の権力関係のなかで,さらには人生の慣れ親しんだ語り方や考え方のなかで理解すること」(white, 2000)だった。それは「困難な状況を経験している人々が自分たち自身を問題として,あるいは何らかの欠損として考えるような誘いが多く存在する」(white & Denborough, 1998)社会的文脈や文化自体を問い直す「言説実践」(Epston, 1998)というべきものである。
「物語を書き換える」という言い方の流布が認知行動療法的に受け取られ誤解が生じがちだが,再著述(re-authoring)とは,社会において好ましいポジティヴな個人のストーリーへと人々を促す類のものではない。むしろ反対に,規範として作用しつつ,人々を方向づけようとする社会のドミナント・ストーリー(ないしはgrand narrative)を批判的に眼差しながら,会話においてそれとは別な場所=オルタナティヴを協働的に探求しようとする。そこでは,文脈/社会あるいは意味から切り離すことのできない「権力」の作用,つまり政治性への自覚が決定的に重要となる。当然のことながら,セラピーもまた一つの文脈であり,その透明性やアカウンタビリティにも関心が向けられる。同じ社会を生きるセラピスト自身もまた,つねに省察の対象とならざるをえない。モンクとゲハードのことばを借りるなら,ナラティヴ・セラピストは「社会政治活動家(sociopolitical activist)」なのだ(Monk&Gehart, 2003)。
そんなナラティヴ・セラピーの気配は,次のようなホワイトのことばからもストレートに伝わってくる。
**
たとえば,虐待を続けてきた男性のセラピーを例にあげよう。この手の男性を病理化し,彼らを逸脱と考えることで,私は,男性として,男性の暴力と,攻撃性,支配,そして征服の価値を維持しているこの文化における男性のための支配的在り方や考え方とのあいだのつながりを曖昧にすることができる。それによって,私は,男性として,この手の支配的な在り方や考え方の再生産に自分も共犯している方法への直面化を回避できるようになる。それによって,私は,男性という階級のメンバーとして,機会不均等を永続化する男性特権の廃止,抑圧構造の脱安定化,そして他者を征服して周辺化するさまざまな権力実践への挑戦に貢献すべき行為に出る責任への直面化を回避できるようになる。そして,それによって,私は,脱資格化,差別などの問題を提起することやそれを終結させるための行為に出ることを,最も権力のない立場にある諸個人任せにしておくことができるようになる。(『ナラティヴ・プラクティス―会話を続けよう』第3章 権力,精神療法,そして異議の新しい可能性.pp.62-63.)
力の差異を認めることは,こうした理由から不可欠なのです。と同時に,もしも私たちがこの力の差異から逃れられないという事実を本当に認めるならば,セラピーの文脈をより平等にするために,私たちは,私たちにできる行為に絶えず気を配るようになるでしょうし,セラピー自体の過程を貫くアカウンタビリティのさまざまな形式をつくりあげるよう弛まぬ努力をするようになるでしょう。(『人生の再著述』6.アカウンタビリティについての会話.p.266.)
**
ナラティヴのこれから──ケア・コミュニティ・身体
〈ナラティヴとケア〉の結びつきからこぼれがちなものがありはしないか,むしろこぼれてしまうものの方──〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉な地点──を見ようとすることが必要ではないか,少なくともそれがナラティヴ・セラピーだ,とここまで書いてきた。
それは,〈ナラティヴとケア〉の世界に意味や価値がないということではまったくない。むしろ「ケア」の思想と実践は,わたしたちをとりまく社会的文脈を考えれば重要度をますます高めるだろうし,〈ナラティヴとケア〉という視点もいっそう精緻さを求められて必要とされていくだろう。ただこのとき,まさにその「ケア」こそが,〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉に眼差されなければならない,ということなのだ。
「ケア」という相互行為や関係性は,わたしたちを育み,支え,守り,認める。でも同時に,そこは社会的文脈と「力」による支配という政治性を抜き取ることのできないリスキーな時空でもある。よいケアとそうでないケアがある,ということとは別の,それ以前の,「ケア」そのものに内在する〈暴力性〉のようなものにどれだけ繊細さをもってクリティカルに迫れるか。その〈暴力性〉に自分が無縁でないことにどれだけ粘り強くとどまっていられるか。ナラティヴ・セラピストならそう努めるだろうし,ナラティヴ・アプローチのなかにナラティヴ・セラピーがあることの存在意義もそこにあり続ける。
同様のことは,〈ナラティヴとコミュニティ〉をめぐる議論とも地続きだ。ナラティヴ30年の背景をなす社会的文脈なかで,わたしたちは「コミュニティ」についても,つながりや再生のイメージのもとに期待を寄せた。「居場所」というワードが頻出したし,当事者研究などにも熱い視線が注がれた。「ナラティヴ・コミュニティ」という切り口を参照しながら,ナラティヴ・アプローチの視点でそれらを検討する仕事はこれからも続くだろう。重ねていえば,そこに価値があるからこそ,「コミュニティ」もまた〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉に問われなければならない。「そんなことがおこるはずがない」と思われる良き場所に深く差し込む権力勾配やコントロールの実相を,クリティカルに捉える必要に気づいたのも,コロナ禍を含むこの30年だった。
物語という形式において人々が意味を生きる存在であることに関心をよせるのがナラティヴ・アプローチであるゆえに,「ケア」と「コミュニティ」はこれからもナラティヴの磁場として意味を持ち続ける。その二つの主題にもつながっていく予感をいだきながら,わたし自身が解像度をあげていきたいのは,ナラティヴと身体/情動をめぐる問題系である(小森他,2023)。ナラティヴが語り,聴くことにおける相互行為として成立する以上,身体性の次元は,もう目の前に差し出されている。そして再度繰り返すなら,身体や情動という,易々と「内側」ないし「個体」化されがちなものこそ,最大限に〈ポリティカルでクリティカルでソーシャル〉に扱われなければならないということ──ナラティヴ・セラピーの見晴らしは,これからもそんなふうに開けていく。
文 献
- Epston, D. (1998)Catching up with David Epston:Collection of Narrative Practice-based Papers published between1991&1996. Dulwich Center Publications. (小森康永監訳(2005)ナラティヴ・セラピーの冒険.創元社.)
- 小森康永・岸本寛史・安達映子・森岡正芳(2023)ナラティヴと情動.北大路書房.
- Monk, G. & Gehart, D. R. (2003)Sociopolitical Activist or Conversational Partner? Distinguishing the position of Therapist in Narrative and Collaborative Therapies. Family Process.42(1);19-30
- White, M(1995)Re-Authoring Lives. Dulwich Center Publications. (小森康永・土岐篤史訳(2000)人生の再著述.ヘルスワーク協会.)
- White, M(2000)Refractions on Narrative Practice. Dulwich Center Publications. (小森康永・奥野光訳(2021)リフレクションズ.金剛出版.)
- White, M(2011)Narrative Practice : Continuing the Conversation. W. W. Norton. (小森康永・奥野光訳(2012)ナラティヴ・プラクティス:会話を続けよう.金剛出版.)
- White, C. & Denborough, D. (Eds.)(1998)Introducing Narrative Therapy : A Collection of Practice-based Writings. Dulwich Center Publications. (小森康永監訳(2000)ナラティヴ・セラピーの実践.金剛出版.)
画像
安達映子(あだち・えいこ)
所属:立正大学社会福祉学部
資格:臨床心理士
著書:『ナラティヴ・コンサルテーション』(小森康永と共著,金剛出版,2022)ほか。
趣味:「本とリゾートとお酒」の3点セットを探求すること