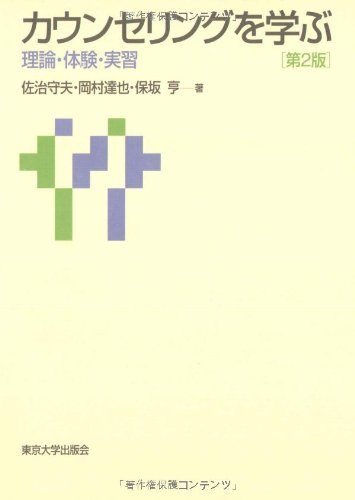飛田鮎太(あしかがの森足利病院)
シンリンラボ 第35号(2026年2月号)
Clinical Psychology Laboratory, No.35 (2026, Feb.)
私の場合,自分でルールを作って,読書を楽しんでいる。
2023年には,「『ロージァズ全集』(全23巻,1966〜1972,岩崎学術出版社)を月1冊読む」という企画を立ち上げ,昨年無事全巻を読了した。まあ,「読んだ」というより「見た」に近い巻も多々あったけれど。
印象的だったものをいくつか挙げる。
①『担任教師による身体障害児の治療(アクスラインとの共著)』(第5巻)
アクスラインの事例にロジャーズがコメントしている(と言われている)論文。アクスラインの応答,それらへのロジャーズのコメントに痺れた。そうか,セラピーってこうやってするものだったと思い出し,全然できていない自分を発見もした。また,「やっぱりクライアント中心療法は厳しいセラピーだ」とも思った。
②『復員兵とのカウンセリング(ウォレンとの共著)』(第11巻)
提示された事例では,ロジャーズ(たち)が,神経症,トラウマ,性別不合,家族支援など幅広いクライアントたちと会っていたことが分かり,その実践に身震いした。前半は,クライアント中心療法についてコンパクトに解説されているので,総じて「ロジャーズによるクライアント中心療法入門」として最適ではないか,と思った。
③『分裂症者とのサイコセラピィの研究から学んだこと』,『クライエント中心療法(Arieti.S(Eds)『American Handbook of Psychiatry Vol.Ⅲ』(1966)の一章)』(第15巻),『分裂病との接触(ジェンドリン著)』(第17巻)
ロジャーズたちの統合失調症へのカウンセリングは,モチベーションの低い,あるいは拒否的なクライアントとのカウンセリングにも,大変参考になる。私なりにエッセンスを要約すると,「クライアントが体験しているとセラピストが思うこと(つまり,セラピスト自身の体験過程や逆転移)を,言語化して伝える」である。自分なりにずっとやってきた(と思っている)ことだが,励まされた。
昨年はもう一つ,浜田寿美男にハマった。『発達心理学再考のための序説』(1993,ミネルヴァ書房)をはじめとする雑誌『発達』連載シリーズ全4巻(『意味から言葉へ』(1995),『身体から表象へ』(2002),『私と他者と語りの世界』(2009))を皮切りに,『私というものの成り立ち』(1992,ミネルヴァ書房),『私とは何か』(1999,講談社),『自白の心理学』(2001,岩波書店),『虚偽自白を読み解く』(2018,岩波書店)などを読んだ。
浜田の「その人がどう体験しているか,それを理解しよう」という一貫した姿勢に惚れた。ロジャーズの共感論「クライアントの内側からの視点(internal frame of reference)を共感的に理解すること」に通ずるところあり,とも思う。
例えば,その自閉症論(『私というものの成り立ち』)「自閉症の中核は「相互主体性(他者との間で〈能動—受動〉のやりとり関係)の成立の困難」であり,それが「他者視点の理解の困難」,「他者との三項的共有関係の成立の困難」をきたすことによって,様々な「症状」が出現する」は,私にとって,彼らと交流するための足がかりとなっている。
さらに,「逆に言えば,私も,世界も,自己も,他者も,あるいは空間も,時間も,そしてこれらを語る言葉も,すべてが自他関係の中にあるパースペクティブ性のもとに成立し,これが私たちの生活世界を基礎から枠づけている」という指摘は,我々がなぜ自閉症を理解するのが難しいのか,を考えるヒントとなり,真に臨床的であると思う。
閑話休題。座右の書の紹介であった。
私の座右の書は,佐治守夫・岡村達也・保坂亨『カウンセリングを学ぶ【第2版】』(2007,東京大学出版会)である。
初版(1996)が,学部1年時の「臨床心理学概論」(著者の一人でもある岡村達也先生が担当。入学して最初の「心理学」の授業であった)の教科書だったこともあり,思い出が詰まっている本である。
院生時代,有志の仲間で輪読したことも,修了後10年間は,1年に1回再読することをマイルールにしていたことも懐かしい。
昨年の日本心理臨床学会第44回大会自主シンポジウムで,発表する機会を得た(『自分のPCAの実現を支えるもの』,企画者・司会者:小林孝雄,話題提供者:真澄徹,藤沢聡子,飛田鮎太)。
ここ数年一人で読書をし,悶々と考えていたことを吐き出した(この記事も,その独習の一端である)。
シンポ当日は,私がPCAから学んだと思うこと(必要十分条件の私的定義・言葉集め)を述べ,「私にとって,PCAとは常に達成されないことの確認においてのみ達成されうるものである」,石原吉郎の『詩の定義』から「詩とは書かない衝動である」をカウンセリングになぞり「カウンセリングとは治さない衝動」と宣った。
そのシンポの直前,ふと本書を手にとった。
第1部「理論学習編」第1章「カウンセリングの定義」を読んで衝撃を受けた。「私が発表しようとしていることは,全てここに書いてある」と。
例えば,以下の引用。
「もし「援助」が,関係の中で相手に何かを与え何かをしてやり,その結果としての相手の治癒ないし改善を期待する働きである,と誤って考えていた読者がいるなら,その考えを放棄したところに「援助的関係」が始まることを銘記したい。援助とは,そのような与えること,してあげること,その結果としての改善への期待を最小限にした活動である」(p.13)
自分が発見したと思っていたことは,なんてことはない,自分が最初に学んだことであった。
第2部「体験学習編」では,著者たちによる体験学習の位置づけや,各種体験学習についての紹介がある。そして,なんといっても,ここには「カウンセリングの学び方」入門,その心得が書かれている。
例えば,以下の引用。
「要は,ことカウンセリング学習に関して言えば,アレコレの学習をした,体験をした,知識を得たということではなく,それぞれの学習を自分自身の体験過程と照合し,その体験の意識化を目指す中で進められたものでなければ,カウンセリングの学習としてはほとんど意味をなさないということである」(p.108)
そして,「真のカウンセリング実践は,ここ,すなわち理論学習即体験学習,体験学習即理論学習においてしかありえない」(p.159)と言い切る。カウンセリング学習者・実践者として,常に胸に刻んでいたい。
第3部「実習編」では,遊戯療法,カウンセリング,スーパーヴィジョン,ケースカンファレンスの様子が,逐語を交えた事例記録と共に提示されている。私にとっては,第1章第3節のカウンセリングの事例が印象的だ。事例のカウンセラーは「カウンセリングを学び始めて6年目」とあり,大学院を修了して4年目くらいだろうか。院生時代,仲間と本書を輪読していた時,「修了して5年くらい経ったら,自分もこんなカウンセリングができるようになるのか」と淡い期待を抱いていた(密かな目標としていた)が,大学院を修了して20年目の今,果たしてこのカウンセラーのようなカウンセリングができているかと思うと覚束ない。
また,長く一人職場であったためか,4,5年前まで「自分は初学者」という感覚でいた。が,いつの間にか職場でも地域の勉強会でも若い人たちが増えた。自分もいよいよ「教育」に多少なりとも寄与する立場になってきたのか……などと考えていた折,第2部第2章「シミュレーション学習の進め方」や,第3部第2章「スーパーヴィジョン」,第3章「ケースカンファレンス」は響いた。
例えば,以下の引用。
「どんなやり方にせよ,事例検討においてはクライアントの問題にのみ焦点を当てるべきではなく,それにかかわるカウンセラーの態度,ありようや行動,カウンセリング関係の特質やその推移を十分に明らかにする努力が払わなければならない」(p.136)
仲間との体験学習・実習の機会では,カウンセリングの解説者(だけ)ではなく,学習者(カウンセラー)の伴走者に(も)なりたい。
最後に,『全集』を(一応)読了してから本書を再読すると,第1部はクライアント中心療法の神髄が見事にすくい上げられている,としみじみと思った(美味であった)。さらに第2版(2007)からは,クライアント中心療法の発展(セラピストの第4条件「プレゼンス」やプラゥティのプリセラピー)の紹介,第2部と第3部では学習における体験過程の重要さの強調もあって,本書を,本邦随一のクライアント中心療法の入門書,とも読める。ただ,本書の射程は,より広く,そしてより深い(と思う)。ここに書かれていることは,「ある既存の理論をもとに,自分なりのカウンセリング理論の構築,及び自分なりのカウンセリング実践を行う」という著者たちの在り様であり,そこから学ぶことは今なお多い,と思った。
本書は「よくわかる」,「かんたん」には書かれていない。また「明日からすぐ使える」ことも書かれていない。本書に書かれていることは,日々の実践にもがき,折に触れて読み返した時,そっと(場合によっては厳しく)読者を励ましてくれる,著者たちの歩み,である。
(とびた・あゆた)
所属:あしかがの森足利病院
資格:公認心理師,臨床心理士
著書:下山真衣 編『知的障害のある人への心理支援─思春期・青年期におけるメンタルヘルス』(分担執筆,学苑社,2022年)